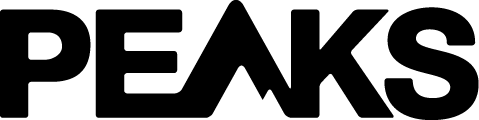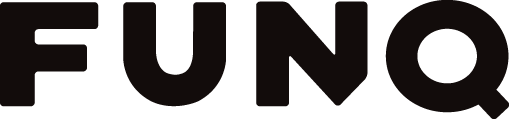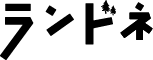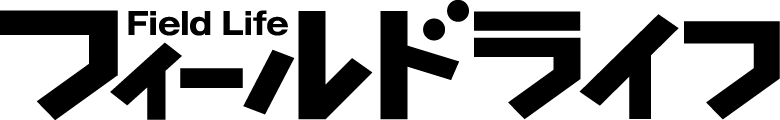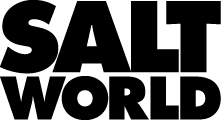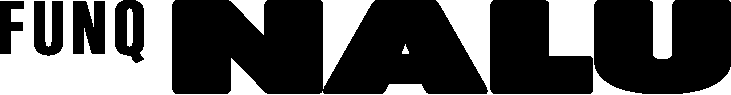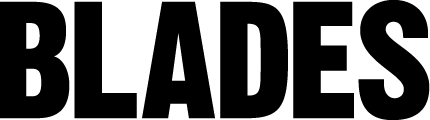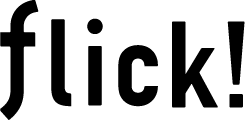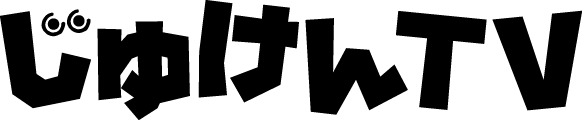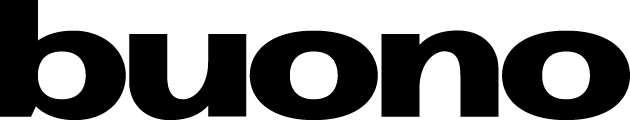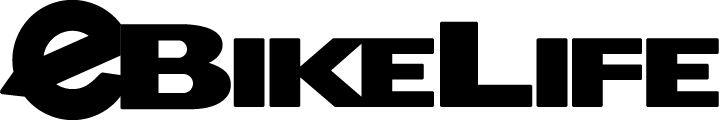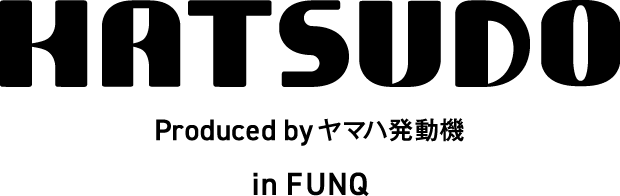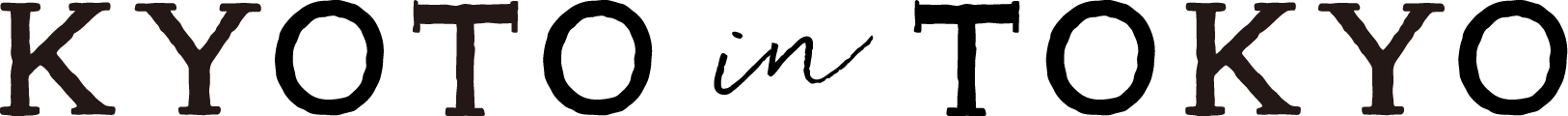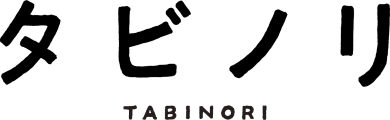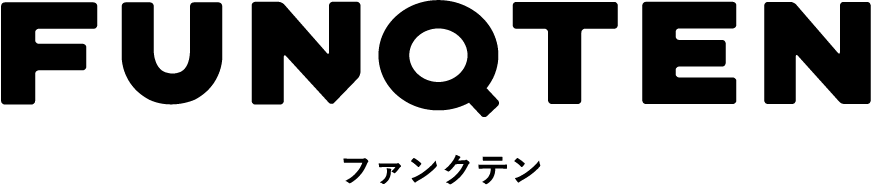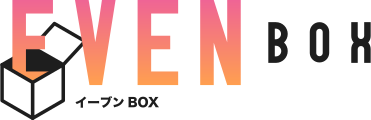初心者目線でソロテント泊の“重さ”を徹底調査◆必要装備をまとめてチェック!
PEAKS 編集部
- 2025年07月23日
INDEX
テント泊は必要な装備が増えるぶん、背負う荷物が重くなる、といわれているが、道具の軽量化が進んだ現在、実際にはどれくらいの重さに収まるのだろう?
答えになるような資料がないので、調査チームを組んで調べてみた!
編集◉PEAKS編集部
文◉吉澤英晃
写真◉後藤武久(人物)、 熊原美惠( 道具)
メンバー
(右奥)PEAKS営業担当/水谷大志:趣味のキャンプを通じて野営の心得はあるものの、山でプライベートのテント泊は未経験。荷物はなるべく軽くしたいけど食事にはこだわりたい派。
(右手前)山岳ライター/吉澤英晃:大学探検部&社会人山岳会出身。前職が登山用品を扱う会社の営業マンだったこともあり、道具の知識には自信がある。最近、登山ガイドの資格を取得した。
(左)アドベンチャーディバズ代表/北村ポーリンさん:テント泊デビューをめざすプログラム「テントむし」を10年以上主催。何百泊以上のテント泊で培った知識で多くの登山者にテント泊を指南している。

ミッション
1. テント泊に必要な装備を見直そう!
2. ニーズに合うおすすめモデルを考えよう!
3. ベースウェイトを調査せよ!
テント泊は背負う荷物が重くなると当たり前のようにいわれてきた。山小屋に泊まるより必要な装備が増えるのだから、それは決して間違っていない。ただし、山道具が年々軽くなっている状況を考えると、テント泊装備の総重量も年々軽くなっているのが当然だろう。重くなるとはいえ、何十キロも背負うことにはならないはずだ。では、現代のテント泊装備の標準的な重さは、一体どれくらいになるのか?本企画はこの疑問がきっかけとなって立ち上がった。
調査するにあたって、極端な軽量化を避けるために、初心者目線を重視することにした。初心者の要望に合う道具一式の総重量を調べれば、現代のテント泊装備の標準的といえる重さを知ることができるのではないだろうか。今回、テント泊初心者を代表するのは、PEAKS営業担当の水谷大志。彼のニーズに合う道具を北村ポーリンさんと吉澤英晃(筆者)が探す流れで話を進める。と、その前に、まずはテント泊に必要な装備をおさらい。ここが調査の出発点だ。
ミッション1:テント泊に必要な装備を見直そう!
吉澤英晃(以下、吉):テント泊の装備は人によって異なるので、基本に立ち返って、まずは必要最低限と思われる装備を考えましょう。
北村ポーリン(以下、ポ):必要最低限だと下段の写真のような内容になるでしょうか。ここに飲み水と食料、燃料が加わるイメージです。
吉:飲み水、食料、燃料は山行日数などで重さが変わる装備なので一覧から省いてOKです。重さが変わらない装備の総重量をベースウエイトといい、今回はベースウエイトを調べようと思います。
水谷大志(以下、水):イスとテーブルは要らないですか?あと、テントの下に敷くアンダーシートも入ってないですね。
ポ:イスとテーブルはキャンプでは用意するのが当たり前ですが、登山では贅沢品。あると快適にすごせますが必須装備ではありません。
吉:アンダーシートは使っている人が多いけど、これもなくていい装備かな。普段使わないけどテントの底に穴があいたことはないし、帰宅後に汚れを落としてからしっかり乾燥させて保管しているおかげで、10年以上劣化せずに同じテントを使い続けられています。
水:そのほかの欄にある“大きめのビニール袋”はなんですか?
吉:これは雨や結露で濡れたテントを包むためのもの。テントの中で荷物を整理するときにも役立ちます。

①テント一式
②スリーピングバッグ
③スリーピングマット
④バーナー
⑤クッカー
⑥ウエア
・レインウエア
・行動保温着
・着替え&タオル1枚
⑦バックパック10 そのほか
⑧ヘッドランプ
⑨ファーストエイドキット
⑩そのほか
・ライター(点火用具)
・カトラリー
・歯ブラシ
・携帯電話、財布
・モバイルバッテリー
・大きめのビニール袋
・地図、コンパスなど
ミッション2:ニーズに合うおすすめモデルを考えよう!
■カテゴリー1:テント
吉:まずはテントから水谷くんの要望を聞いていきましょう。
水:室内が広くて、雨を気にせず靴などを外に置いておける前室付きで、その前室はしっかり調理をしたいのでなるべく広いものがいいですね。それと、短辺側から出入りするのは窮屈な感じがするので、入り口は長辺側にあるモデルが理想です。
吉:前室付きだとフライを被せるダブルウォールが第一候補ですね。
ポ:前室が広いテントだと、ライペンの「オニドーム」があります。室内には鬼の角のように外側へ飛び出る空間が二箇所あって、そこに荷物を置くと居住スペースを効率的に使える特徴も魅力です。入り口は長辺側にあるから、理想にぴったりではないでしょうか。
水:重量はどうでしょう。いまの山岳用テントの重さはどのくらいが一般的ですか?
吉: 肌感覚だと、1人用で1,300g前後。1,000gを下回ると超軽量という印象があるね。オニドームの1人用の最小重量は1,290gで、張り綱やペグといった付属品を含めると1,510g。わりと一般的な重さのソロテントといっても差し支えないでしょう。
水:なるほどです。ちなみに細かいことですが、フライシートの色はテントを選ぶときに気にしたほうがいいものでしょうか?
ポ:経験上、黒は暗すぎて落ち着かないのと、赤は逆に興奮する感じがして落ち着かず眠りづらい印象です。あと、薄いグレーや白は内側が透けやすいので、とくに女性は気にしたほうがいいですよ。

■ライペン/オニドーム1
・¥53,900
・使用サイズ:間口148(最大230)×奥行122(就寝部82)×高さ97cm
・問)アライテント

CHECK:もっと軽くしたいなら……
いまはダブルウォールテントで1,000gを下回るモデルもめずらしくない。オニドームと同じブランドのライペンからリリースされている「SLソロ」はそのひとつ。さらに軽量化をめざすならツエルトやシェルターと呼ばれるタイプも候補に挙がる。ただし、1,000g以下の軽いテントやツエルト、シェルターは、一般的な重さのテントと比べると強度や快適性が劣る場合があるので、扱いには注意が必要だ。

■ライペン/SLソロ
・¥63,800
・最小重量:900g
・使用サイズ:間口205×奥行90×高さ95cm
・問)アライテント
【COMMENT】
水:広い前室が◎。調理を行ないやすいし、サイズが大きい登山靴も置きやすそう!

■カテゴリー2:スリーピングバッグ&マット
吉:続いてスリーピングバッグとマットです。水谷くんはキャンプが趣味だから両方ともすでに持っているんじゃないかな?
水:スリーピングバッグはイスカの「エアドライト480」を使っています。マットはクローズドセルとセルフインフレーティングタイプをそれぞれ持っていて、普段は2枚を重ねて寝ています。ただ、それでも地面の寒さと凹凸が伝わり、寝苦しさを感じているところです。
ポ:スリーピングバッグはそれで十分。快適使用温度が0℃前後のものを選べば登山の3シーズンのテント泊に対応できます。
吉:スリーピングマットは寝心地に優れるエアマットを選んだほうがよさそうですね。試しにポーリンさんの私物に横になってみたら?
水:フカフカしていて寝心地がまったく違う!これなら快適に眠れそうです。ただ、自分の体格だと両腕がマットから落ちてしまいました。マットに厚みがあるぶん、この段差は気になりますね。
吉:それなら、横幅が広いワイドサイズを選ぶといいよ。ちなみに、軽さを優先すると長さはショートがおすすめだけど……。

水:足りないマットの長さを補うために、バックパックを足元に置く方法を今回初めて知りました。でも、やっぱり長さは全身をカバーできるレギュラーサイズほうが寝心地がいいです。
ポ:マットを2枚重ねても寒さを感じるというのが気になりますね。おそらく、断熱性(R値)は合わせて4相当になるはずなので、それ以上のスペックをもつモデルを選んだほうがよさそうです。
吉:ちなみに、エアピローは必須装備ではないですか?
ポ:それは贅沢品!スタッフサックに服を詰めたもので十分です。

■(上)イスカ/エアドライト 480
・¥50,600
・快適使用温度:-7℃
・問)イスカ
■(下)サーマレスト/ネオエアー X ライト NXT(RW)
・¥42,900
・使用サイズ:64×183cm
・R値:4.5
・問)モチヅキ
【COMMENT】
水:マットは幅64cmのワイドサイズ。多少重くても寝心地重視で選びました。

CHECK:もっと軽くしたいなら……
スリーピングバッグは保温性を下げればそのぶん軽くなるが、寒くて眠れない事態に陥らないように。足りない保温性をウエアで補おうとすると、かえって総重量が増えてしまう落とし穴にも注意しよう。スリーピングマットは横幅が約50cmのショートサイズ一択。R値を下げればエアマットで200g台のモデルを選択できる。クローズドセルマットにはさらに軽いモデルがあるが、厚みが薄くなり寝心地は悪くなる。

■(上)ニーモ/テンサーエリート(ショート マミー)
・¥33,000
・重量:215g
・使用サイズ:51×160cm
・R値:2.4
・問)ロータス
■(下)ラブ/ミシックウルトラ 120 モジュラー
・¥77,000
・重量:330g
・快適使用温度:0℃(R値4以上のエアマットを使用した場合)
・問)ランドアール
■カテゴリー3:クッカー&バーナー
吉:水谷くんはクッカーとバーナーもキャンプ用に持っているとか。
水:ただ、キャンプ用なので、とにかく大きくて重たいです。でも、調理しやすい点は気に入っているので、登山用には料理を作りやすい軽いクッカーと、ゴトクがしっかりしているバーナーがほしいです。
ポ:クッカーにはエバニューの製品がよさそう。小型のフライパン、炊飯用のアルミクッカー、軽量なチタンクッカーなどが揃っていて、すべて重ねられるのでコンパクトに持ち運べます。バーナーはSOTOの「マイクロレギュレーターストーブウインドマスター」がおすすめで、付属のゴトクとは別に4本ゴトクを選べます。
吉:クッカーとバーナーは料理をしっかり作りたいかどうかによって用意するものが変わってきますね。たとえば、食事をアルファ化米とフリーズドライだけで済ませれば、クッカーはお湯を沸かすためにひとつあればよくて、バーナーは3本ゴトクでも十分。“食事をどうするか”が選ぶポイントといえるでしょう。

①エバニュー/ U.L. Alu Pot 700 ¥7,810、UL/ ALU ナベ 700の蓋 ¥2,310
②エバニュー/U.L.Alu Pan 14cm ¥7,480
③エバニュー/ Ti570FD Cup ¥3,190
④エバニュー/ Ti 400FDCup ¥2,420 問エバニュー
⑤SOTO /マイクロレギュレーターストーブウインドマスター¥9,350、ウインドマスター専用4本ゴトク フォーフレックス ¥2,090
問)新富士バーナー



■カテゴリー4:ウェア
吉:レインウエアは日帰りでも泊まりでも登山の必須装備ですね。
ポ:すごく軽いモデルもありますが、生地が薄すぎると物理的に寒さを感じやすいので、北アルプスなど標高の高い山でも使うことを考えると、初心者の方にはおすすめしていません。生地の厚みはファイントラックの「エバーブレスフォトン」くらいあったほうが安心です。
水:着替えが少ないのは、1泊2日の想定だからですか?
ポ:日数が増えても、着替えは上下&靴下&下着のワンセット。旅行の感覚だと日数分の着替えが必要と考えがちですが、登山では基本、着替えません。入山から下山まで同じウエアですごすのが普通です。
吉:ダウンジャケットなど、いわゆる保温着も要らない?
ポ:行動中に着る行動保温着は必須ですが、夜に寒さを感じるようならスリーピングバッグに入ればいいので、さらに保温着を増やす必要はないというのが私の考え。ただ、もちろん体力に余裕があれば保温着を荷物に加えてもOKです。


■カテゴリー5:バックパック
水:必要な装備を並べてみると、荷物の点数がだいぶ少ない。これなら40 ~ 45ℓくらいの容量でも余裕でパッキングできそうです。
ポ:それでもテント泊には50ℓくらいあるバックパックがおすすめです。容量に余裕があるほうが荷物をパッキングしやすいし、1泊以上の計画にも対応できる。あと、下山後のお土産も入れられます(笑)
水:バックパックの重さはどのように考えればいいでしょう?
ポ:飲み水、食料、燃料まで含めた、最終的に背負う重さがポイントです。すべてをパッキングした状態でも10kgを超えないようなら、軽めのモデルを選んでも快適に行動できますよ。
吉:ただ、重さが10kgを超えると剛性の高いバックパックが欲しくなりますね。ヒップベルトが丈夫で厚みがあるものほど、重たい荷物を背負ったとき肩や背中にかかる負担が少なくなります。

■ラブ/ムオン50
・¥38,500
・容量:50ℓ
・問)ランドアール
【COMMENT】
ポ:普段背負っている愛用モデル。10~12kgまでなら快適に背負えます。


■ミステリーランチ/グレーシャー50
・¥55,000
・容量:57ℓ
・問)エイアンドエフ
【COMMENT】
吉:荷物が10kgオーバーでも肩が痛くならない剛性が魅力。重量は重いけど体への負担は少ないです。

ミッション3:ベースウエイトを調査せよ!
吉:今回はラブの「ムオン50」を背負う想定で、詳しく見てきた装備とそのほかの必要装備をすべてパッキングして、ベースウエイトを量ってみましょう! 結果は……“6.47kg”です!
水:おぉ~ ! 過度に軽量化してないのにとても軽く収まりましたね。
吉:ここに飲み水、食料、燃料を加えても、1泊程度なら10kgを超えなさそう。もう少し軽いスリーピングマットを選んでクッカーの数を減らしたら、ベースウエイト5kg台も不可能じゃなさそうですね。
ポ:主催しているプログラムでテント泊初心者を見ていると、着替えやタオルを何枚も持ってくるひとが多いです。あと、値段の安いテントやスリーピングバッグとマットを買って、それがすごく重いこともあります。
吉:今回の調査結果がテント泊装備を見直すきっかけになるといいですね。




※この記事はPEAKS[2025年8月号 No.173]からの転載であり、記載の内容は誌面掲載時のままとなっております。
**********
▼PEAKS最新号のご購入はAmazonをチェック
SHARE
PROFILE

PEAKS 編集部
装備を揃え、知識を貪り、実体験し、自分を高める。山にハマる若者や、熟年層に注目のギアやウエアも取り上げ、山との出会いによろこびを感じてもらうためのメディア。
装備を揃え、知識を貪り、実体験し、自分を高める。山にハマる若者や、熟年層に注目のギアやウエアも取り上げ、山との出会いによろこびを感じてもらうためのメディア。