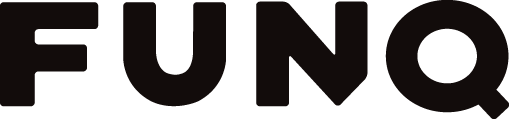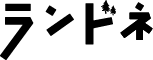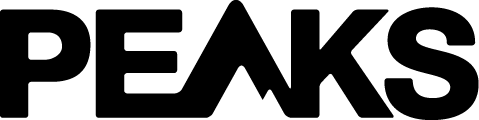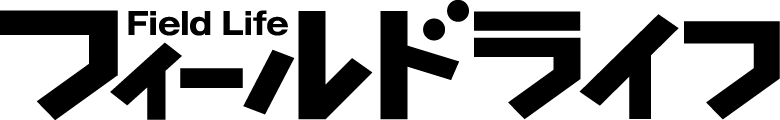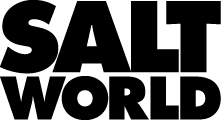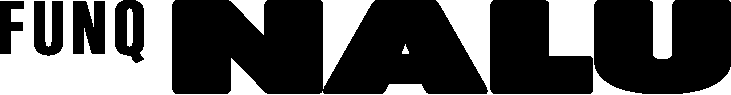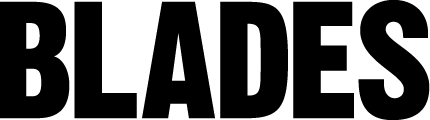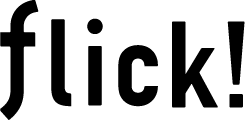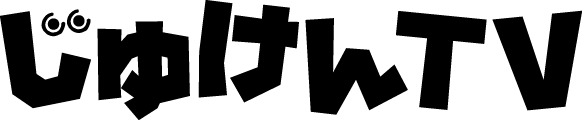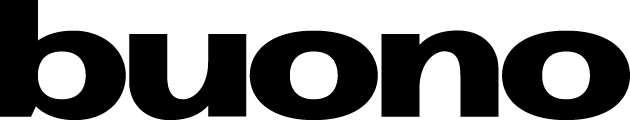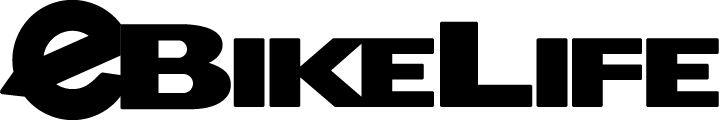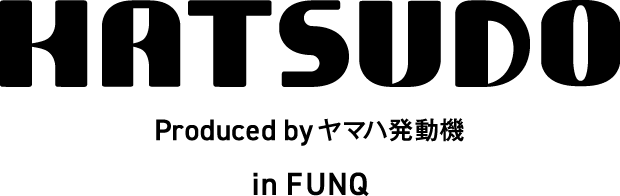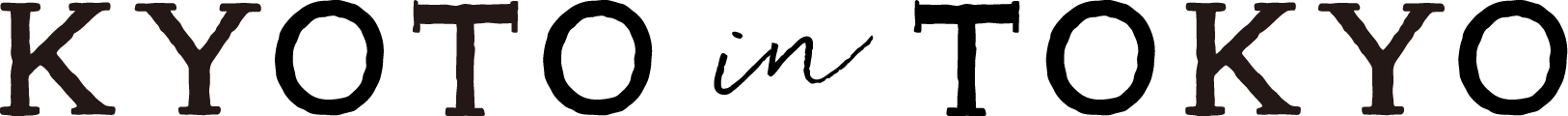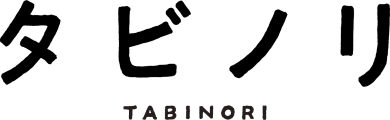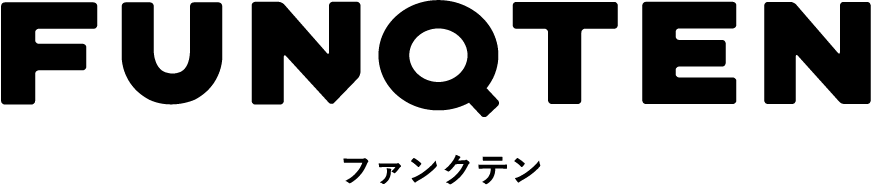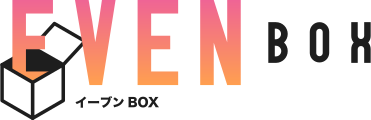ピナレロのスペシャリストたちは新型F7をどう見るか?|PINARELLO
安井行生
- 2025年10月30日
INDEX
フレーム価格100万円オーバー、完成車価格200万円オーバーというスーパーハイエンドバイク、ドグマの売り上げがかなりの割合を占めるというイタリアのピナレロ。さすがロードバイク界きってのハイブランドだが、そのドグマ以外のモデルはどうなのか。ピナレロの専門店「ペダリストピナレロショップ」横浜店店長の山崎泰史さん、青山店店長の福本元さん、ジャーナリストの安井というピナレロに造詣が深い3人がモデルチェンジしたばかりの新型F7に試乗し、語り合った。
新型ピナレロ・Fシリーズとは


2024年に発表された11代目となるドグマF。それから1年を経て、新型Fシリーズがデビューした。
ケーブルルートをコラム両脇からコラム前面へ変更してヘッドチューブをスリム化、それに伴ってコラム断面が真円から楕円になったことや、その楕円コラムに合わせた専用ハンドルを装備したこと、さらに空力性能を高めた各チューブの形状など、前作からの変更点はドグマに準ずる。ドグマ同様のレーシングモデルながら、タイヤクリアランスを32Cとし(ドグマは30C)、太めのタイヤを装着するユーザーにも対応した。なお、フレーム形状は見比べても違いが分からないほどドグマFに酷似しているが、金型は別ものである。

ラインナップは価格が上からF9、F7、F5、F3、F1という5モデルで、奇数の数字が振られる。日本に入ってくるのはF3を除く4モデル。F9~F5は同じフレーム形状で、F1のみ旧型Fシリーズの形状を流用する。ちょっとややこしいが、F9とF7のフレームは同じもの(フレームの一部に東レのT900使用)、F5はそれがT700に、F1は乗り心地を重視したT600となる。
どのモデルも完成車での販売となり、
- F9(デュラエース完成車、モスト・ウルトラファストホイール、208万円)
- F7(アルテグラ完成車、フルクラム・レーシング800DB、105万円)
- F5(105Di2完成車、フルクラム・レーシング800DB、72万円)
- F1(105完成車、シマノ・WH-RS171、47万円)
という構成だ。なお、F9とF7には一体型カーボンハンドルであるモスト・タロンウルトラファストが装着される。

価格だけを見れば、200万円を超えるF9は他社でいうところのハイエンド帯、F7がF9と同じフレームを使ってパーツで価格を下げたセカンドグレードとなり、ドグマFがスーパーハイエンドと呼ばれる特別な存在ということが分かる(完成車で250万円~)。

今回はピナレロを専門に扱うショップ、「ペダリストピナレロショップ横浜」の山崎泰史店長と、「ペダリストピナレロショップ青山」の福本 元店長という2人のスペシャリストと共に、新型F7の試乗を行った。

F9とF7には、ステム一体型専用ハンドル、モスト・タロンウルトラファストが付く。トレンドであるフレア形状を取り入れつつ、空力を重視したステム一体型カーボンハンドルである。

フォークコラムは前作の真円断面(右)から、横方向に広い楕円断面(左)に。これによってブレーキケーブルのルートがコラム両脇からコラム前面へと移動した。ヘッドチューブを縦に薄くして空力性能を向上させるためだ。
 タイヤクリアランスは前作の30mm(右)から32mm(左)へ。太いタイヤを履くユーザーにも対応する。
タイヤクリアランスは前作の30mm(右)から32mm(左)へ。太いタイヤを履くユーザーにも対応する。
 ハンドリングと安定性を高めるため、フォークオフセットは43mmから47mmへと伸ばされている。
ハンドリングと安定性を高めるため、フォークオフセットは43mmから47mmへと伸ばされている。
ロードバイクの完成形に近づいた

安井:今日は先代F7と新型F7を比較することができました。見た目に大きな変更はありませんが、印象はいかがですか。
山崎:新型は安定感が上がりましたね。おそらくジオメトリの変更によるものでしょう。ホイールベースが伸びたことによってバランスがよくなってます。僕は普段440という小さめのフレームサイズに乗っているんですが、ハンドルを切ったときにつま先が前輪に当たりやすいんです。でも新型はフォークオフセットが長くなっているので、その心配が少なくなります。安定志向になったとはいえ、加速などの動力性能は落ちていません。先代F7もいいバイクですが、乗り比べてしまうと新型のほうが完成度は高いですね。
福本:先日、ライドイベントで先代F7で120kmほど走りました。その印象をもとに今日の新型と比べると、若干ですが先代のほうがソリッドというか、レーシーな硬さを感じました。新型はタイヤが30Cになってホイールベースが伸びた影響なのか、いい意味でマイルドになった印象です。路面からの衝撃も新型のほうが優しいですね。しかし、変に柔らかいとか走りが重いというわけではなく、先代にあった高い運動性能は維持しつつ細かい部分をブラッシュアップすることで脚に優しく扱いやすくなったという印象です。トータルではロードバイクの完成形に近づいたと感じます。

安井:僕の印象もお二人とほぼ同じです。そもそもピナレロのミドルグレードは、「踏めないほど硬いわけではなくペダリングしやすいのに、動力性能のレベルは高く、濃厚なトルク感がある」ことが美点でした。ピナレロはアルミフレームの時代からハイエンドバイクの存在感が非常に強く、それがゆえにミドルグレードの影が薄いメーカーですが、そのような「ハイエンドバイクにはない美点」を持つミドルグレードが多かった。今回試乗した新型F7ですが、先代にあったそういうピナレロらしさはきっちりと残っています。フレームは新設計ですが、ちゃんとそこが残っているということは、おそらく開発チームが「Fシリーズはこう走らせたい」という意志を持っていたんだと思います。
福本:そうですね。
安井:そこは残しつつ、安定感が高まったように感じます。ダンシングやコーナーなど、二輪車が不安定になるようなシーンでの安定感が増して、安心して走らせられるようになっていました。一言でいえば、お2人が言われたようにバランスがよくなった。いいモデルチェンジだと思います。

山崎:そういう変化によって、新型は幅広い方に合うバイクになったと感じます。新型の安定感、扱いやすさは、初めてロードバイクに乗られる方でも安心でしょう。
福本:はい。ただ、今回新型になってタイヤが30Cになったので、純正ホイールのリム幅19mmはちょっと狭めです。タイヤの性能を最大限に発揮させることを考えると、リム幅23mm以上のホイールを入れてあげるとより完成形に近づくのかなと。
安井:確かに。
F7の価値とは?

福本:お客様の先入観として、「ドグマはレース専用バイクで、F9もF7も同様にレース志向の人々に向けたバイクだ」という印象を持たれている方が多いんですが、僕は「ハイエンドバイクになると目的が制限される(レースにしか使えなくなる)」というよりは、「ハイエンドに近づくにしたがってどんどん上限が引き上げられていく」というイメージでご説明しています。どのモデルでもロングライド的な走りは楽しめます。F5であればホビーレースで活躍できますし、F7やF9であればシリアスな登録レースを戦うに十分な性能です。ドグマFはもちろんワールドツアーレベルで通用する。要するに、このF7は始められたばかりの方から、レベルの高いレースまで幅広くお勧めできるバイクだと思います。ピナレロならではのサイズラインナップの豊富さもポイントですね。
安井:ドグマという絶対的なアイコンがある中で、F5は価格がグッと下がるので「手が届くピナレロ」という独自の価値を持っていると感じます。ただ、F9やF7は他メーカーのミドルグレードよりも高価なので、どうしても影が薄くなってしまう。しかし、そういう存在にしておくには勿体ないと思いますね。もっとF9やF7の価値は知られるべきです。

福本:そうなんですよ。僕らサイクリストって、数年で乗り換えを前提にしているところがあると思いますが、このF7は「ぜひ10年乗ってください」といえる完成度です。自転車としては高額ではありますが、これに乗ることで得られる経験の幅はかなり広いと思います。
安井:正直、価格とスペックだけを見れば、もっと優れたモデルはありますね。それでもこのFシリーズを選ぶ価値はどこにあると思いますか?

山崎:やはり「ピナレロ」というイタリアンブランドを冠していることは大きいでしょう。車でもそうだと思いますが、所有する憧れがあるブランドが存在しますよね。それらに共通しているのがあるとすれば、もちろん歴史や性能、そして塗装ですね。この新型Fシリーズにも、ドグマFレベルの塗装が数多くラインナップに加わりました。走る喜びに加えて、所有する喜びも大きいと思います。走っても持っても眺めても楽しめる。そういった魅力が今回の新型からはより強く濃く感じられるようになったと思います。
安井:スポーツバイクは家電などの実用品と違って趣味のものですからね。性能とかコスパだけでは語れません。
山崎:その通りです。

福本:確かに、単純なコスパで比較するような選び方では筆頭には出てこないと思います。売る側としては、そういう方に無理にピナレロをお勧めしようとは思っていません。これは決して高級ブランドの高飛車な目線ではなく、求めるものが違うと思うんです。「あのレースのあのカテゴリで上位に入賞したい」とか、「富士ヒルでタイムを短縮したい」といった目的があるならば、予算のなかでそれに沿ったものがあると思うんです。でもやはりピナレロというブランドのバイクには、「自分が乗っているピナレロという自転車は、他のものにはない価値がある」という高揚感があります。乗り物なので機能・性能は大事ですが、ブランドの歴史、美しさ、カラーやデザインと性能をここまで両立できているブランドは他にはないんじゃないかなと。トップブランドという立ち位置にあぐらをかかず、毎回きっちりと進化させてくるところも尊敬に値します。だから、万人に乗ってほしいというよりは、このブランドを愛してくださっている方に乗ってほしいと思います。
PROFILE

山崎泰史(左)
ピナレロショップ「ペダリストピナレロショップ横浜」店長。
福本元(右)
中学生でロードバイクに乗り始める。高校で自転車競技部に入り、
ペダリストピナレロショップ青山

ピナレロを専門に扱うワンブランドショップ。青山と横浜に2店舗を構える。商談と作業は完全予約制(予約はHPの予約フォームから)で、ピナレロというブランドに相応しい落ち着いた接客を受けることができる。ロードバイクスクール事業も実施しており、青山店の地下にはフィッティングルームがある。
SHARE