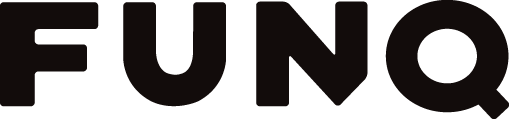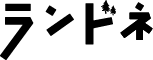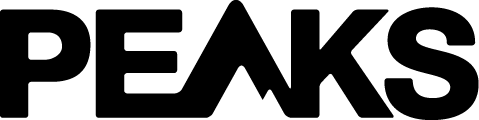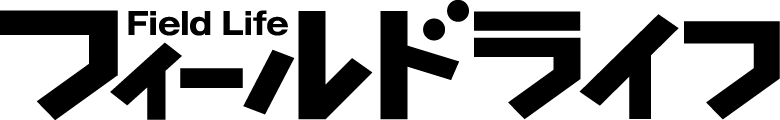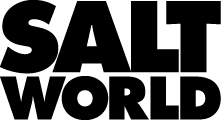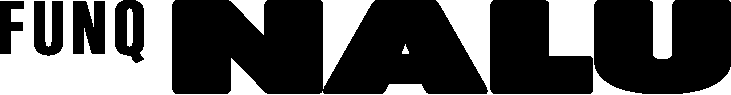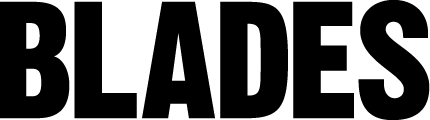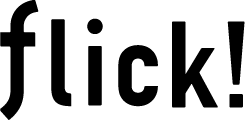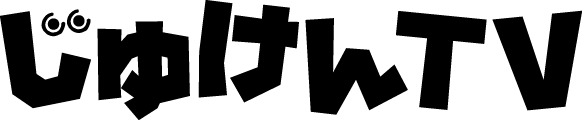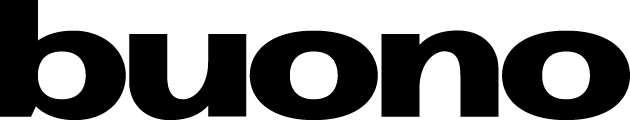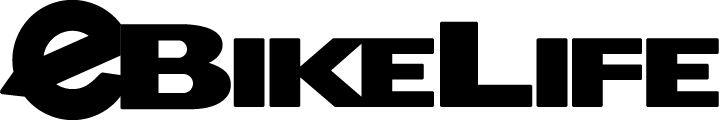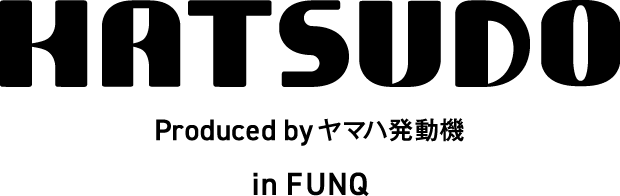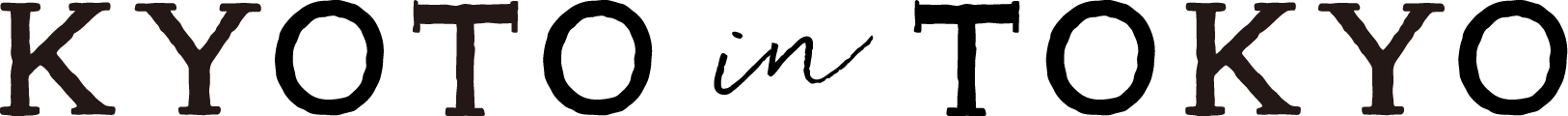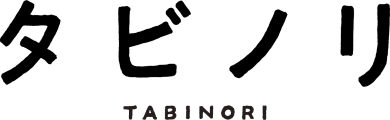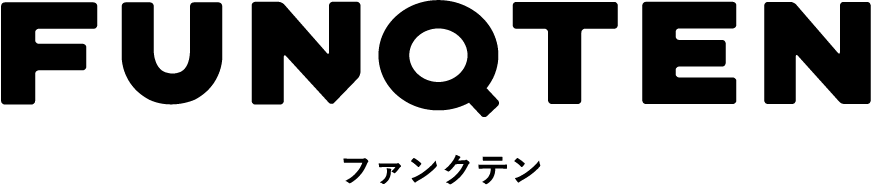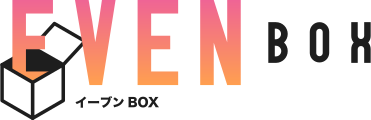MTBツーリズムの未来像! Setouchi Vélo協議会「広島県安芸太田町ミーティング」開催
Bicycle Club編集部
- 2025年07月08日
INDEX
2025年6月2日、広島県安芸太田町にて「Setouchi Vélo協議会 広島県安芸太田町ミーティング」が開催された。自転車、特にマウンテンバイク(MTB)を活用した地域振興を軸に、先進事例の共有と今後の展望について多角的な議論が交わされた。広島県や安芸太田町の行政関係者に加え、長野県白馬村からのゲストスピーカーやサイクルメディア関係者も登壇。人口減少や高齢化が進む山間部における観光政策として、MTBが持つポテンシャルを活かすことの可能性を示す機会となった。
地域資源を体感するトライアルライド

午前中には、参加者約40名によるEバイクでのトライアルライドが実施された。
スタート前にはオージーケーカブト柿山昌範さんによるヘルメットの正しい着用方法や、プロライダーでもあるコイデルの門田基志代表らによるEバイクの操作講習なども行われ、安全管理と受け入れ体制の成熟度がアピールされた。これは、サイクルツーリズムを通して観光客の受け入れにおける関係者にとって重要な知識である。

Eバイクを使ったトライアルライドは龍姫湖「温井ダム」をスタートとする18kmほどのコースで行われた。安芸太田町が誇る自然景観と里山の地形を生かした内容となっていた。

途中には地元でも人気があるお菓子が味わえるエイドステーションも設置され、参加者は地元の有志からの歓迎を受けた。単なるサイクリングにとどまらない「体験型観光」としての魅力を肌で感じた。


首長の挨拶で広島県安芸太田町ミーティングがスタート

午後からのミーティングでは、まず開催地を代表して安芸太田町の橋本博明町長が「人口減少率・高齢化率が高い安芸太田町にとって、交流人口を創出するサイクルツーリズムは希望の光」と語った。

またSetouchi Vélo協議会会長でもある広島県の湯﨑英彦知事からは、ビデオメッセージが寄せられた。
メッセージの中で知事自身も昨年5月に、安芸太田町をマウンテンバイクで温井ダムの湖畔や林道を走ったことを報告。Setouchi Vélo協議会に参加する関係者と情報を共有することで、今後の取り組みや政策の検討に資する貴重な機会となることを期待すると発言、広島県としてマウンテンバイクを活かした地域づくりにかける期待を述べた。
広島県全体をMTBのフィールドに

ミーティングでは開催地である広島県そして安芸太田町から発表があった。
広島県観光課の木津早苗参事は「MTBの拠点づくりに向けた取り組み」をテーマに広島県の取り組みについて発表、「広島県全体をMTBのフィールドに」を合言葉に、地域の自然・文化・暮らしを体験価値として磨き上げていくことが発表された。
山林が豊かな広島県ではMTB拠点づくりへ

広島県はしまなみ海道に続く新たな観光ブランドとして「やまなみ」構想を紹介し、安芸太田町を県有林のMTBの拠点候補地とする計画を明かした。
この背景には欧州ではMTB市場が年々拡大しており、2024年には約5,770億円、2029年には1兆円超の市場規模が見込まれており、森林資源が豊富な広島県にとって、この流れに乗ることは地域振興と国際観光戦略の両面で重要とされている点がある。
具体的には県北の安芸太田町を候補地とし、既存施設や豊かな自然環境を活用してインバウンド需要に応える体験型観光を目指す。スキー場や公園を転用した事例に学びつつ、E-MTBを軸とした誰もが楽しめるコース設計とガイド人材の育成を進行中だ。
2024年には株式会社ジャイアントとサイクルツーリズム推進に関する覚書を締結。林道を活用したMTBコースの整備や、温井ダム周辺でのガイド育成研修をスタート。
今後はマウンテンバイクの拠点構想の検討が進められており、将来的には、しまなみ海道のように、持続可能な観光モデル構築を目指すとした。

広島市中心部から車で約1時間の安芸太田町。周辺には既存の宿泊・飲食施設や駐車場も整っている。さらに、温井ダムリゾートを起点にした全長約30kmの林道を通るコースを活用可能で、カヤックや森林セラピーなど多彩なアクティビティとの連携が期待されている。

里山資源を活かした安芸太田町のサイクルツーリズム戦略

安芸太田町の下村佳世参事は「里山を生かしたサイクリングの取り組み」をテーマに取り組み事例を紹介した。

安芸太田町では豊かな自然環境と地域資源を活用し、交流人口の拡大と地域活性化を目指して「サイクルツーリズム」の推進に取り組んでいる。2016年には北広島町と連携して「やまがたサイクルツーリズム推進協議会」を設立し、自然・文化・食など地域の魅力と結びつけた多様なサイクリングコースを整備。初心者からベテランまで楽しめる6つの推奨コースが用意されており、案内標識や休憩施設も拡充しているという。
「Fun Rideひろしま」や女性向けツアー、スタンプラリーといったイベントを通じて、地域とサイクリストとの接点を創出。エイドステーションでは地域産品によるおもてなしも行われており、地域とのつながりを強化している。

また、温井ダム周辺ではウォーターアクティビティや宿泊施設の整備が進み、サイクルツーリズム、特にマウンテンバイクを活かすことでの相乗効果による滞在型観光の可能性も広がっていくとしており、令和7年度から、地域おこし協力隊を活用したサイクリングコースの開発等を進めていく予定である。また、広島県と連携し、コース設定と併せてサイクリング拠点構想を検討していく。これらの多角的な取組は、人口減少が進む中山間地域において、持続可能な地域づくりのモデルケースとなりうるとした。
白馬村の実践から学ぶ基調講演
続く基調講演には、白馬マウンテンバイククラブの原知義代表が登壇。「MTB先進エリア白馬村でのMTBを活用した取り組み」について発表した。
白馬村の事例は、既存の観光資源を活用しつつ、スポーツを媒介とした新たな経済循環を生み出す点で注目される。原さんは「経済効果だけでなく、住民の誇りや外部人材の流入という点でも大きな変化があった」と語った。

白馬村では、冬はスキー、夏はマウンテンバイクという季節型の観光活用により、通年型の地域経済を構築している。その中心にあるのが「白馬岩岳マウンテンバイクパーク」であり、スキー場のリフトインフラをそのまま活用した「ダウンヒル型」のフィールド展開が高い評価を受けている。
白馬マウンテンバイククラブの原知義代表は制度的課題についても触れ、日本では森林の所有権や土地利用に関する法的制限が多く、MTBが自由に走れるフィールドは限られている。こうした制約の中で、地域が一致団結してスキー場や民間地を活用し、フィールド整備・運営を持続的に進める仕組みを構築したことが、白馬の大きな強みとした。
小学生向けのMTB教室とクラブ活動や中高生の部活動化と社会体育としての展開
白馬村では2012年から、地域の小学生を対象に自転車教室をスタート。参加者はMTBではなく“ルック車”(形だけMTB風の自転車)ばかりで、整備の必要性も痛感したという。
2017年には岩岳エリアにアジア最長のコース(6km)が誕生し、クラブとして正式に活動を開始。「日本一幸せな放課後」をコンセプトに、週1の月曜練習会や水曜のダウンヒル練習を実施しており「子どもたちがリレー形式で走る”駄菓子リレー”や、景色の良い展望台までの登坂、クイズラリーなど、遊び心も満載です」と語り、すそ野を広げる活動を行っている。
さらに2023年からは、中高生の部活動としての位置づけも持ち始め、地域の大人と子どもが共に練習できる環境を整備。部活動の課題は、指導者、練習場所、用具の確保。協賛を募りながら、25の地元企業がクラブジャージに協賛するなど、地域全体の支えで自立した活動を展開しているという。
地域インフラとサイクリング文化の醸成

このほか毎年秋には「平林安里選手と走ろう3時間耐久レース」を開催。じゃんけんで勝ったチームがアメをもらえる「CANDY BIKE FES」や、春の清掃活動と合わせた「タンデム流鏑馬選手権」、地元作家による「友情メダル」など、子どもから大人まで楽しめる企画を多数実施するほか、海外交流では、ケアンズMTBクラブと姉妹クラブ提携を結び、国際大会への参加やホストとしての交流も行っている。
大人の趣味としてのMTBだけではなく、子どもたちや地域を巻き込んで自転車に関心を持ってもらうための工夫を紹介した。
多角的視点が交差したパネルディスカッション

最後のプログラムとして実施されたパネルディスカッションでは、「山間部におけるサイクルツーリズムの可能性」をテーマに、行政・メディア・現場実践者が登壇した。
メンバーは安芸太田町の橋本博明町長、広島県観光課の木津早苗参事、白馬マウンテンバイククラブの原知義代表、オサカナ農園自然学校の小坂利隆代表、サイクルスポーツ編集部の迫田賢一統括編集長、バイシクルクラブ編集部の山口博久編集長の6名、コーディネーターはMTBライダーとしても知られる株式会社コイデルの門田基志代表が務めた。
議論では、マウンテンバイクを活用した里山資源の教育的価値、インバウンド戦略としてのMTBの可能性、受け入れ体制の整備課題など、様々な切り口から意見が交わされた。

地元の活動についてはオサカナ農園自然学校の小坂利隆代表から紹介があり、安芸太田町を拠点に自然体験と教育活動として自転車を活用しており「子どもたちと一緒に100kmのロングライドをしたこともあります。自転車は移動手段であると同時に、学びのきっかけになるツールです」と地元住民に自転車を知ってもらうための活動例を示した。

白馬マウンテンバイククラブの原知義代表は、自身の経歴を踏まえ、かつて大会運営において企業主導で始まったイベントが継続できなかった経験を紹介。「補助金やスポンサー頼みでは活動は続かない。自分たちがやりたいと思えることを、持続可能なかたちで進めていく必要がある」と語り、そのうえで「楽しいと思えることを、周囲に共有していく姿勢が重要だ」と提言した。地域に根差した民間の活動の大切さを示した。

広島県観光課の木津早苗参事は行政は主導ではなく支援役に徹するべきとして、地元からの提案を県として地域活動のサポートをしていくことを示した。

バイシクルクラブの山口博久編集長は「広島県の湯崎知事はマウンテンバイクに乗られる方、そのビジョンを活かしてマウンテンバイク文化を作っていただきたい」と広島県へ期待を示したほか、アクティビティとしてのマウンテンバイクの可能性を示唆。海外では、親がライドを楽しむ間に子どもがスクールに通える環境が整っており、「家族で楽しめる仕組みづくりが鍵になる」と提案。広島市内から1時間ほどとアクセスのよい安芸太田町ならばその可能性があると述べた。
メディアの立場としてサイクルスポーツ編集部の迫田賢一統括編集長は、トライアルライドでの視察と全国の旧街道を巡る旅を通じて得た体験と照らし合わせ「今日のコースは全国で走った中でも屈指の内容だった。旧街道には地域の暮らしと歴史が息づいています」と安芸太田町の印象を語り、山間部でのサイクルツーリズムの可能性を示した。

終盤では、橋本博明町長も発言。「安芸太田町でも、地元の人たちが自分たちで走り、案内し、受け入れる。そうした“顔が見えるツーリズム”を進めたい」と語った。

コーディネーターを務めたコイデルの門田基志代表は自身のマウンテンバイクでの競技活動を通して経験した事例を紹介。さらにインバウンドや観光に加え、マウンテンバイクが抱えるトレイル問題など多岐にわたる話題を取りまとめた。
行政、メディア、現場の担い手が一体となって、自転車を軸とした地域振興のあり方を模索する姿勢が随所に見られるディスカッションとなり、予定時間を超えて活発に展開され、登壇者たちの思いとビジョンが交差する場となった。
- BRAND :
- Bicycle Club
SHARE
PROFILE

Bicycle Club編集部
ロードバイクからMTB、Eバイク、レースやツーリング、ヴィンテージまで楽しむ自転車専門メディア。ビギナーからベテランまで納得のサイクルライフをお届けします。
ロードバイクからMTB、Eバイク、レースやツーリング、ヴィンテージまで楽しむ自転車専門メディア。ビギナーからベテランまで納得のサイクルライフをお届けします。