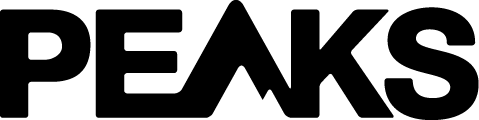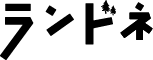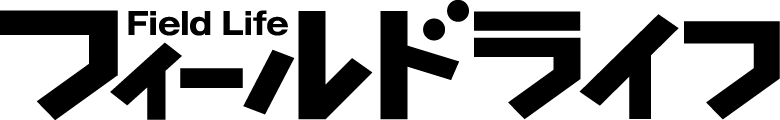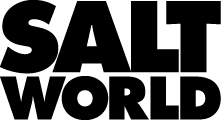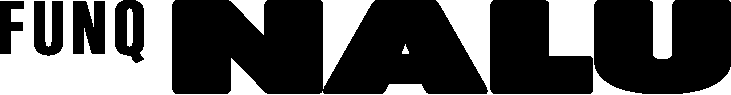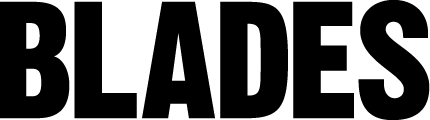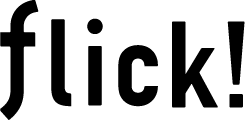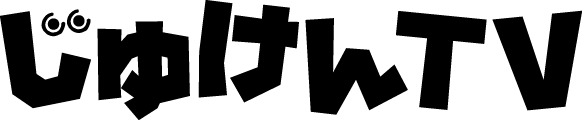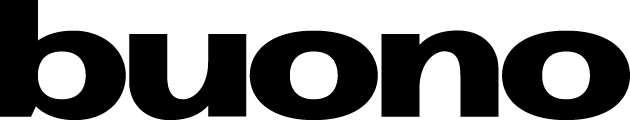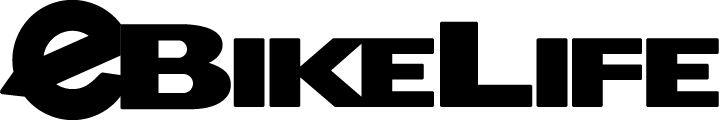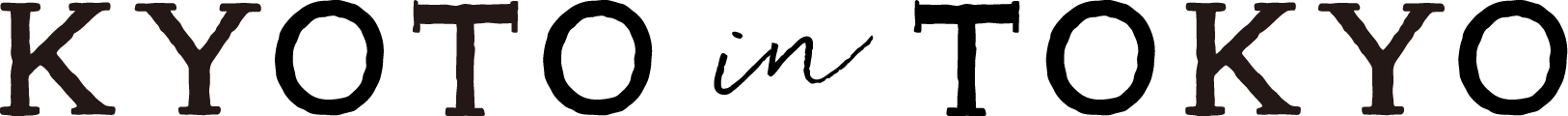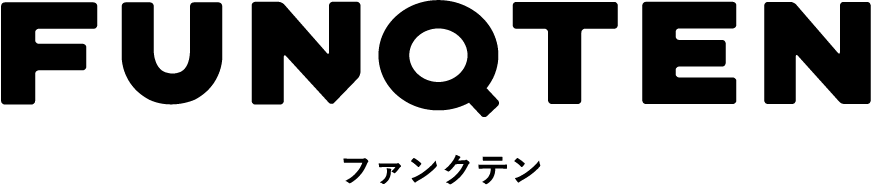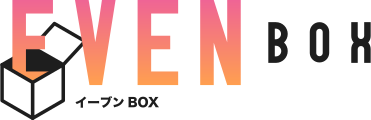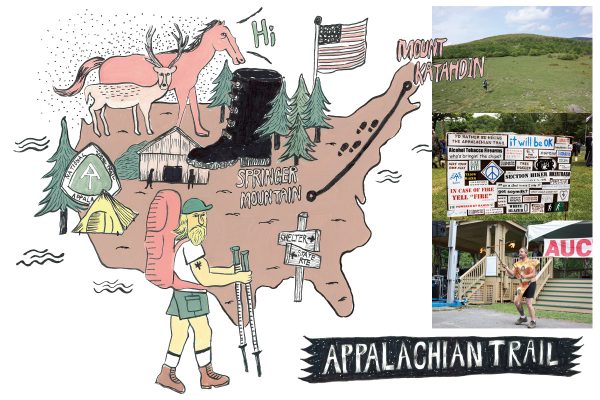会心の1本を求めて。パキスタン・カラコラム 最奥の地を目指した7年間(前編) Riding the Last Frontier of Karakoram 2023
WILDERNESS 編集部
- 2025年12月22日
INDEX
コロナ禍を挟み、8年ぶり、8冊目の『WILDERNESS』が発刊された。おもに海外でのアウトドアアクティビティを中心に、キーワードは「冒険」や「探検」という、(カジュアルではない)遠征ツアーなどにスポットを当てたカテゴリーの雑誌である。だれもが気軽に実践できる内容ではないけれど、アウトドア好きなら読み物として楽しんでいただける一冊を目指した。その発刊を記念して、2023年に行なわれた「パキスタン・カラコラム第1次遠征」の特別寄稿をお届けしよう。
編集◎WILDERNESS編集部
文◎佐伯岩雄
写真◎國見祐介
旅の始まりは長野から

「岩雄さん、来年3月にパキスタンに滑りに行きませんか」
2019年2月の末、家族で長野県小谷村の里山に滑りに行ったとき、偶然に再会した佐々木大輔(大輔)から突然言われたことが始まりだった。現場で妻の承諾を得て、遠征に参加することを即決した。
だれもいない最奥の地で、自分たちだけで思い思いのターンを刻み楽しむ。そのようすを映像や写真に残して、帰国後には各地の報告会キャラバンでたくさんの方々と楽しみを共有したい。それが旅の目的。
目指すは、パキスタン北部のラトック山群を取り巻く全長約180kmの氷河。ソリに荷物を積んでキャンプをしながら人力で旅する。長距離の移動や標高5,000mを超えるところで50度の斜面を滑ることなど、すべてが未経験で不安もあったが考えるだけで興奮した。
メンバーはすべて、隊長の大輔が声をかけて集まった者たちだった。5月末に大輔、小西隆文(コニタン)、中川伸也(シンヤ君)と私の4人で、北アルプスの剱沢にてロープワーク、レスキュー等を訓練するための合宿を行なった。大輔とは長年付き合いがあり何度もいっしょに滑ったが、ほかのメンバーとは初顔合わせだった。4日間という短い期間だったがすぐにおたがいを理解し、信頼関係を築くことができた。
合宿初日のようすをSNSにアップしたところ、スキーガイド資格の受験中だった伊藤裕樹(イトウ)が突然に電話をかけてきて、自分も参加させてほしいと言ってきた。大輔は「じゃあ今晩10時までに岩雄さんのログハウスに来られたら考えてやる」と言った。
剱沢から下山後、私の家のログハウスで酒を飲みながら日程や装備、ルートなど、遠征計画のミーティングを行なっていると、(すっかり忘れていたのだが)10時ちょうどにログハウスのドアが開いた。イトウだ。住所もろくに伝えていなかったのにもかかわらず、仕事を終えて約束の時間に現れた。
遠征の準備とトレーニング

私は山岳ガイドを職業としているのだが、より負荷の高いトレーニングをしないと58歳になる自分はみんなに迷惑をかけてしまうと思い、1年後の遠征に向けてトレーニングを開始する。この年は積極的に体を動かした。
さらに、5,000mを超えるところでスキーをした経験はなかったので、高度順応と高所での滑りのトレーニングのため、11月に単身でネパールのメラピークに向かった。本番のパキスタンで狙うような急な斜面は滑ることができなかったが、用具や装備などの課題を見つけることができて良い経験となった。
年が明けて1月下旬。何度かのオンラインミーティングを重ね、装備や食料などを現地に送ることができた。この時点で、各々が普段サポートを受けている企業・団体から、映像制作費用として協賛金が300万円ほど集まっていた。もちろん各メンバーは航空券を含めてすべて自費での参加である。
ビザ、航空券の手配などすべて順調に進み、2020年3月20日の出発を待つばかりとなったが、不穏な空気が漂い始めた。2月中旬から世界的にコロナの影響が出始めたのだ。そこで我々も大使館に連絡して現地のようすを確認したが、とくに問題ないとの返答だった。しかし出発の2週間前、突然各メンバーのところに大使館から連絡が入る。「現地の空港は閉鎖された。出国しないでくれ」と伝えられた。世界中を襲ったパンデミックの始まりだ。
海外旅行はおろか国内の登山すらできなくなり、私の地元・立山でも春のアルペンルートが閉鎖された。当時、私は富山駅前で登山用品店を営んでいたが、ロックダウンのなか、これから先もこの地で経営を続けることへの不安から、持て余した時間で実家の納屋を改装して店を移転することにした。
そのときのためにできること
すでにテント、登攀具、食料等の主要な装備は現地に送ってある。いつ行けるともわからないがそのときのために備え、参加メンバーでトレーニングを兼ねた合宿を計画する。ライダーのほか、動画カメラマンの関口雅樹とスチールカメラマンの國見祐介が加わり、2021年3月に鹿島槍北壁、五竜岳武田菱、鳥海山周遊と連続10日間連続の合宿をこなした。壁での登攀システム、ソリを引いての移動及びテント生活。メンバー全員で登り、滑り、実りのある合宿をできたことがとても嬉しかった。
12月上旬、カメラマンを含めた7名(イトウは不参加)のメンバーで北海道合宿を行なう。
十勝岳山麓でのソリ引き訓練とカミホロカメットクでの登攀訓練、カメラマンとのコミュニケーションを深めた。
このとき、懸案であったドローンオペレーターの役割を担うメンバーとして、ライダーの元起大智(ダイチ)がお試し参加することになる。ダイチは私の息子の同級生で私とも長年親交があった。本人の強い希望で参加を申し出たが、ほかのメンバーとは面識がなかった。私の推薦だが一度いっしょに山に行き、隊のメンバーに異存がなければ新たなメンバーに加わるということだった。もちろん隊長が気に入らなければこの話はなくなる。はたして、ダイチは持ち前の体力と気遣い、撮影の技術をかわれて新メンバーとなる。あとにも先にも隊長が直接声をかけていない隊員はダイチだけだ。
2022年春もいぜんとして自由に海外へ行ける雰囲気ではなかった。残念ながらこの年も我々はパキスタンに向かうことができなかった。
それでも諦めてはおらず、4月上旬に我々は再び北海道の大地にいた。目的は暑寒別連峰の雨竜沼湿原を目指し、南暑寒岳、奥徳富岳周辺での滑りと長期間の雪上生活及びソリを使った移動のためのトレーニング。現地での調理方法や食材も試してみた。この機会にソリ(冒険家・荻田さんからお借りしているもの)を制作してもらった「植松電機」にご挨拶し、ソリの調整をしていただいた。今回の10日間の合宿ですでに本番の日数を超える合宿をこなした。
2023年春、そのときは来た

2023年3月15日にイトウ、國見、ダイチの若手3名が羽田空港からパキスタンに向け先発隊として出国した。装備は3年もの間、現地・スカルドゥに保管されている。その保管状況によっては新たに手持ちで持ち込む必要がある。
現地からはテント、シュラフ、コンロ、登攀具等はまったく問題ないとのこと。食料にかんしては麺類が酸化しており食べられないものもあるが、アルファ化米、乾燥野菜は大丈夫との連絡を受ける。装備の確認と必要なものの買い出しが済めば、現地での高度順応、スキー等の活動をするよう隊長から指示(遊びに行っていいぞの許可)が出る。
後発隊の大輔、シンヤ君、コニタンと私の4人は3月23日に代々木のミウラベースで標高4,000m設定の低酸素室に宿泊し、翌日成田空港から出国した。翌深夜、イスラマバードに無事到着。25日から2日間かけ、カラコラムハイウェイで仲間の待つスカルドゥへと移動した。

個人的には飛行機で行きたかったが、フライト予定が合わずにワンボックスカーでの移動となった。ハイウェイとは名ばかりで、断崖絶壁の未舗装路も多く、ドライバーの運転も荒いので山に入る前から緊張の連続を強いられる。
スカルドゥの街で買い物を済ませ、ホテルの夕食は控えめに食べていたが、なにか違和感を感じ、不意にトイレに行きたくなった。これまで経験したことのない下痢、地獄の始まりだった。一晩中ほぼトイレですごし、朝からはキャラバンのスタート地点、アスコーレに向けて6時間のドライブ。朝食も摂らず僅かな水と下痢止めを飲んで極悪の道を進む。
アスコーレではコックが夕食を作ってくれたがまったく食べることができず、個人用テントでアルファ化米をおかゆにしたが半分も食べることができなかった。症状からみてカンピロバクターだと思われるため、日本で処方してもらった大量の薬のなかから抗生物質を5日間飲むことにした。
アスコーレの標高は3,000m。これから4日間かけて標高4,200mの氷河末端までポーターとともにキャラバンを開始する。パキスタンの山には山小屋がほとんどない。そのためキャラバン中はキッチンテントや食堂テント、椅子とテーブル、食材や燃料など大量の物資と、500kgを超える我々の荷物を20人以上のポーターとロバ5頭で運ぶことになる。ポーターはひとり30kg、ロバは一頭80kgを担いでくれる。大変な重労働だが現地の方にとっては貴重な現金収入の機会となっている。コロナが明けて最初の遠征隊とあって、村中から人が押し寄せて熱烈に歓迎された。



私は終始食べることができず、飴を舐める程度で歩くペースも上がらない。ほかのメンバーは高山病対策のためダイアモックスを服用して順調に高度順応していった。もちろん私は下痢なのでダイアモックスなどは飲めない。少しずつ遅れる私を気遣ってみんなはときどき待ってくれているが、やっと休憩かと思ったとたん、合流するとすぐに歩き始める。何度もがっかりし、山で弱い人の気持ちが初めてわかったような気がした。
キャラバンも3日目になると徐々に体力が回復してきて、食事も軽くとれるようになった。気がつくと國見やイトウもつらそうにしていることが多くなった。山では一番弱い者が一番つらい。自分より遅れることが多くなった國見のお陰で少し気持ちは楽になったが、そんなふうに思う自分を情けなくも思った。


4日目にようやく4,200mの氷河の末端に到着する。ポーターとはここでお別れだ。みんなで記念撮影をして労いのチップを渡し、感謝の気持ちを伝える。身軽になった彼らは走るように去っていった。多分村までは2日で帰るだろう。私は抗生物質の服用を終了し、体調もほぼ戻ったが5日間のダメージはその後も引きずることになる。
我々7人だけの静かなキャンプ。これから始まる長い行程を思い気持ちも落ち着いた。ここまですべて移動に費やしたため翌日は休養日となる。これまで体調不良で個人テントにしてもらっていたがここからは3張りのテントで7人が暮らす生活となる。最初に同室となったのはイトウだ。
3張りのテントにはそれぞれの役割があり、3人用のテントは炊事係。2人用テントは水作り、もうひとつの2人用テントはトイレなどの環境整備や用具の修理だ。この役割は最後まで変わることがない。役割の公平な分担と、同じメンバーと居続けることによるストレスの解消のため2、3日おきにテントとメンバーが入れ替わる方式とした。
まず、私とイトウは水作りだ。全員分の飲料水と炊事に必要な水は毎日20L以上に及ぶ。もちろん温かい飲み物も必要なので沸騰させる必要もある。朝食用に10Lのドロメダリーバッグに入れた水は、夜間の冷え込みで凍らせてしまわないないように、ふたりの間で大切に保管する。
あとになって思えば、水作りが一番つらいってことだ。我々のコンロはMSR製のガソリンコンロ。現地のガソリンは質が悪いのか、ときおり不完全燃焼をおこすため都度分解、清掃を行なわないとうまく燃えてくれない。1台は炊事、1台は水、もう1台はメンテナンスだ。これをローテーションさせ、我々が生きるために必要な水をなんとか作ることができた。火はもっとも大切だ。いくら雪があっても火がなければ、我々は白い砂漠で息絶えることになる。
同室となったイトウのようすがおかしい。声をかけると「ご飯は食べられません」と言う。疲れが溜まったのだろう。休養日でよかった。シュラフで寝ているイトウの横で、復活早々大きな鍋でひたすら水作りを行なう。これまで元気がなくみんなに迷惑をかけていたので多少つらくてもがんばることができた。



延々と続く、氷河の果てまで

4月2日、いよいよ気が遠くなるほど長いパンマー氷河のはじまりだ。ソリは5台、先頭の私はソリをひかない。先頭だけが2番目の者とロープで結ばれ、万が一クレバスに落ちても後ろの者がオモリとなって止まる方式だ。
初日、2日目と天候に恵まれ順調に進むことができた。3日目からはまったく視界の効かないなかを進まなくてはならなかった。雪も降ってきて足首までだがラッセルとなる。先頭は目標物がなく、平衡感覚を保つことも困難な状況になる。プローブを腰から引きずり斜面に印をつけ、斜面の変化がないか確認しながら進む。斜面変化のある所はクレバスが隠れている可能性があるからだ。
雪も降るがときおり強い日差しが出ると、今度は雪面が温められソリの裏に氷がついてまったく進まなくなる。暑いのか寒いのかわけがわからなくなる。4日目になると、日中の暑い時間帯は休むことにした。しかしそうすると暗いなかでのテント設営となる。それはそれで結構大変だった。
休養日を挟んで4月7日、ついに我々の前に目標としていた大きな斜面が広がった。大輔が「カラコラムスキーヘブン!」と大きな声で叫んだ。見たこともないような景色が目の前に広がっていてみんな大興奮。我々は雪崩の影響を避けるため、斜面から遠く離れた氷河の真ん中の安全地帯にキャンプを張り、翌日の滑走のためにルート作りに出かけた。
近くに見えるが山が大きすぎて進めどもなかなか近づかない。ようやく斜面に取りつくと見た目より遥かに急傾斜で、しかもスキーを履いているのに膝まで潜るラッセルとなる。先頭のイトウがアイゼンに履き替え、スキーを担いで登りだすが30分かけても10mほどしか進まない。これでは稜線までたどり着くことはできないかと思っていると、業を煮やした大輔がスキーを履いてシール登高を始めた。
50度を超える斜面のため、眼の前の雪をスコップで切りながら進んでいく。50度の斜面に登高角25度、切った雪の高さは肩を超えるほどになる。本人は「カラコラムハイウェイだ!」と言いながら極限のシール登高を楽しんでいるようだった。イトウのほうはロープいっぱいまで直登している。私がフォローしたがこれ以上は無駄な作業になりそうだったのでふたりで下りてきた。それでも高いところから見る景色は絶景だった。

翌日の滑りを楽しみにしながらみんなで夕食を摂り、早めに眠りについた。マイナス26℃の極寒の朝を迎え、朝食のため3人用テントに7人が入った。國見のようすがおかしい。昨夜はほとんど眠れていないようだった。咳き込む國見に大輔が「息を吐いてみろ」と言う。息を吐く國見の喉から「ゴボゴボ」といまにも水が湧き出そうな音が響く。パルスオキシメーターを使って何度もSpO2を測るが50を超えない。機械がおかしいのかと全員で測るがほとんどが80%台だ。
高山病で肺水腫になっていることは間違いなかった。一刻の猶予もないと思った。今日中に高度を下げないと明日まで生きていられる保証はない。ここまで来て滑ることなく下山になるとは思ってもいなかったが、國見の命こそがなにより大切で、第一優先はできる限り早急に高度を下げることだった。
隊長の大輔が午後に下山することを提案する。そして、1本だけ滑ろうということになった。カメラマンとして参加した國見にもみんなの写真を撮りたいとの強い思いがあった。もし体調がこれより悪化するようなら、昼夜問わずソリに乗せてできる限り標高を下げる作戦だ。この判断は隊長の大輔以外には、だれにもできなかったと思う。
前日のトレースを使い9時には全員で稜線に立つことができた。目の前にはラトックの北壁、右手にはオーガ、ビアチェラヒタワーが聳え、圧巻の景色に見惚れる。眼下には自分たちのトレースが延々と続いていた。
メンバーはそれぞれ自分の滑るドロップポイントに向かう。私は大輔から「一番右奥のラインが良くないですか?岩雄さんなら5ターンくらいでボトムでしょう」と言われた。それは綺麗な面でたしかに4〜5ターンで抜けられそうな気がした。
最初のライダーはコニタンだ。自分のポジションからは見ることはできなかったが、無線で聞いている限り、転んだものの立て直して上手く滑り降りたようだった。あのプロボーダーのコニタンが転ぶなんてどうしたのかなと思った。
次は私の番だ。ドロップポイントから見ると綺麗な雪面がボトムまで続いている。自分の視界に入らないほど斜面は急で雪は深い。なんの躊躇もなくいつもどおりまっすぐ滑り始める。1ターン目ですでにトップスピードに乗った。3ターン目で少しスピードを抑えようとして強めに踏み込んだ瞬間、両足の板が深く潜り重心がズレた途端にハイサイドを食らって吹っ飛ばされた。回転しながらものすごいスピードで滑落している。数秒後、空中を飛んだと思ったら激しい衝撃が襲った。懸垂氷河の割れ目に落ちて止まっていたのだ。
無線からは「岩雄さん大丈夫ですか?」とだれかが言っているのが聞こえた。直ぐに周りを確認したが危険な状況ではなく、スキーやストックなどの用具も一切失くしてはいなかった。「大丈夫、みんなのところに戻る」と言って滑り始めた。
振り返ると自分のターンと滑落痕が見える。なんで抑えようとしたのかわからなかった。経験不足だろう。コントロールするくらいなら真っ直ぐ降りて限界を突破したかった。後悔しながら仲間の滑りを見守った。次に滑ったのはイトウだった。もっとも素直なラインを選んでいたがやはり難しい雪にやられて、直ぐに滑落することになった。
4人目は大輔だ。かなり難しいラインを選んだが上部ではしっかり雪質を見極め、コントロールされた滑りで、スピードに乗る最大傾斜を思いっきり攻めた滑りを見せた。猛スピードで追ってくるスラフをかわし、最後は時速100km近いスピードでボトムに抜けていった。


5人目に滑ったシンヤ君は驚くほど美しい滑りを見せた。50度を超える斜面では自分の落とす雪もものすごいスピードで流れる。舞い上がる雪煙のなか、想像を超えるスピードですり抜けていくようすはまさに芸術的だった。このふたりの滑りには心から感動した。
最後にドローンで撮影をしていたダイチが滑る。前のふたりに刺激を受けたのか、思いっきり急な斜面に飛び込んだが一瞬で吹っ飛ばされる。30mほど空中を吹っ飛んだあと5〜6回転して止まった。まるで壊れたおもちゃを見るようだった。まさに若さを感じさせるチャレンジングな滑りだった。
下山開始と、少しの寄り道
全員が滑り終えたがゆっくりしている暇はない。私は身の回りの最低限の荷物と國見の装備を背負う。テント等の装備回収はほかのメンバーに任せ、一足先に國見と下山を始めた。
下りは10度もない緩斜面だ。登ってきたトレースも薄くだが残っている。自分が先に滑れば立っているだけで降りられるはずだったが、國見の板はまったく滑らない。板を外して確認したところ、全然手入れがされていなかった。なんでこんなところに来るのに万全に準備していないのかと腹が立ったが、いまそんなことを言っても始まらない。私の板と交換しようにもブーツのサイズがまったく合わない。仕方がないので一生懸命にワックスをかけて磨いた。
國見は泣きながら「すみません、すみません」と言うが、「とにかく下りないと死ぬから行くぞ」発破をかけた。滑りは多少良くなったが肺に大量の水が溜まっているため呼吸はかなり苦しそうだ。すぐに数十メートルしか立っていられなくなり始める。あとから追いついたメンバーのソリに乗せての移動となるが、がんばっても氷河の斜度はかなり緩いので、せいぜい200mほど下りたにすぎなかった。
國見は夜、横になって寝ることができない。翌日暖かくなった午前中に休んでもらい、その間に近くのゆるい斜面を滑りに行った。緯度が日本とかなり違うなか、太陽は高く、真上から照らされるので快晴なのに斜面の変化がわからずとまどった。午後はイトウをソリに乗せての移動となったが、かなり標高を下げることができ、本人も楽になったようで、大きな危機は脱したと感じられた。


我々は最後にチャレンジできそうなポイントを見つけた。やはり50度を超える斜面で初めに滑った場所よりいろいろなラインを選ぶことができそうだった。今回は2割ほどシールを使うことができたが、ほぼアイゼンでの登高となった。先頭は胸までの雪をかき分けながら登る。イトウとシンヤ君が交代しながらルートを作ってくれた。
今回も撮影の関係でコニタンが先頭で滑る。スムーズで危なげのない滑りだ。次は私の番だが初回に転んでいるので、なんとか転ばずにボトムまで抜けたかった。1ターン目でかなりの雪が落ちる。数ターンすると自分の落としたスラフがものすごい勢いで迫ってくるのが見えた。勝負に出ることはできなかった。スラフから逃げ、やりすごしながら攻めるチャンスを伺っていたがすでに体力は限界にきていた。無難な滑りで終わってしまった。続くイトウ、ダイチも転びはしなかったが無難な滑りで納得していないようだった。
シンヤ君の選んだラインはかなり特殊だった。上部は55度を超える狭いルンゼで、途中少し広がるものの後半に狭く閉じていく地形だった。シンヤ君は左右の壁を使ってまさにサーフィンをしているようだった。壁が閉じ始める手前、グーフィーバンクにきれいに当て込んだと思った瞬間、膨大な量のスラフに飲み込まれていく。縦に回転しながらときおりヘルメットと板が交互に見える。流石にやばいと思った。止まったシンヤ君に無事を確認すると「OK」と。驚きだ。ビンディングが多少壊れたのと軽いムチウチだけだった。

最後にみんなが見守るなか大輔が滑る。滑り出しは5mを超えるマッシュを3段ほど飛び越えその後は60度近いヒマヤラ襞(ひだ)が入った斜面だ。深い雪に足を取られながらも絶妙なバランスで果敢に攻めたが、残念ながら最後は10mほどの滝状のクレバスに頭から落ちてしまった。このとき、スキーを片方失くしてしまった。その後は國見のスキーを使用しての下山となった。
國見をソリに乗せ、我々は氷河の末端、4,200mの最初の地点まで戻ってきた。本来なら反対側のビアフォー氷河に迎えのキャラバンが来る予定だったが、衛星携帯電話で現地エージェントにもとのところまで来てくれるようお願いする。迎えを待つ3日間、暇つぶしに反対側に見えたマエダン氷河に遊びに行く。まさかこのとき、再びこの氷河に来ることになるとは思いもよらなかった。
旅の終了、そして──

いろいろあったが我々の旅は終わった。計画から4年、この遠征のために各地からメンバーが集まってトレーニングを重ね、遠征に向かった。もちろん終われば地元に戻ってまた普段の仲間と活動する。出発前に「ワールド・ベースボール・クラシック2023」が開催されていた。(レベルは天と地ほどの差があるが)大谷翔平選手が「1日でも長くこのチームで野球をしたい」と言っていた。私もまさにそんな気持ちだった。
悲しい連絡。2024年1月6日、長い時間をともにすごしたイトウが北岳に行って帰らないとの連絡が入る。北岳バットレス登攀後、行方不明となった。4月に入り我々も捜索に入ったが残念ながら見つけてあげることはできなかった。彼の所属する山岳会も毎週捜索に入ったが、結局発見されたのは7月だった。またいっしょに山に行こうと約束していたのに残念でならない。もっと美味しいものを食べさせてあげればよかった。もっと優しくしてあげればよかったとの思いが募った──。
旅の第2章(後編)は12/23発売「WILDERNESS NO.8」にて掲載しています。
SHARE
PROFILE

WILDERNESS 編集部
知的好奇心旺盛なアウトドア好きを、さらなる冒険の世界へ誘うメディア。国内外の秘境や圧倒的な自然現象を取材した多彩なルポで掘り下げ、好奇心と行動を刺激する内容で奥深き自然を旅する魅力を伝えます。
知的好奇心旺盛なアウトドア好きを、さらなる冒険の世界へ誘うメディア。国内外の秘境や圧倒的な自然現象を取材した多彩なルポで掘り下げ、好奇心と行動を刺激する内容で奥深き自然を旅する魅力を伝えます。